1950年、東京生まれ、内山節(うちやま たかし)という哲学者がいる。たしか2021年初頭にYouTubeでこの人の存在を知り、いくつか動画を視聴した。そうして今回、地元の図書館で内山節著作集を発見したので、そのうちの一冊を手に取ってみた。
この人の研究テーマは労働である。こんな言い方はしていないが、いわば労働哲学だ。今回初めて手にした著作、内山節著作集3『戦後日本の労働過程』はタイトルの通り太平洋戦争後から執筆時の1980年までの日本人の労働について扱っている。デビュー作も『労働過程論ノート』という題名であり、やはり労働が生涯の研究テーマであるようだ。
この人の主張がどんなものか、まずは著作集3の中から少し引用しよう。ここにエッセンスが詰まっている。
1970年代の不況以降、企業のいわゆる減量経営と実質賃金の横バイないしは低下に耐えながら、多くの人々にわかってきたことは、やはり自分は労働者であったというもっとも単純な事実であるように思う。しかしそれに気が付いたとき、自分は労働者であると居直る場所がどこにもなくなっていたという事実を発見せざるをえなかった。職場において、組合において置かれた世界は、すべて従業員の世界であって、労働者の世界ではなかった。
p.40
戦後、1950年代に日本ではテーラー・システム、ないしフォード・システムが導入され、生産の分業化・合理化が進んだ。そのときに生産設備や労働形態も大きく変わり、従来の労働者のあり方も解体された。そこから70年代の高度成長に至るまで労働は資本の側がコントロールするものとなり、生産性は上がったがかつての労働者が自分の労働をつくりだすというあり方、あるいは労働者の連帯は失われてしまった。今やかつての意味での労働者はおらず、みな従業員に、つまりサラリーマンになってしまった。
と、これが大枠の認識と言って間違いないだろう。
つまりは戦後間もなく始まった生産体制の改革によって、豊かな労働者のあり方が失われてしまった。これを内山氏は嘆いているのだと思う。
引用した著作は1980年時点でのものだが、状況は40年が経過した今でも基本的には変わっていない。企業は経営者が全体を設計し、部門ごとに従業員を割り当てる。労働者が自分で仕事をつくりだすことは例外的だ。労働者にとってはどの企業に所属するか、その企業内のどの部署・ポジションに身を置くかが重要で、労働内容は二の次とされている。
変わったことといえば、労働者が従業員としても満足できなくなったところだろうか。労働内容は脇へおくとしても、日本企業は従業員に一定の給料と雇用を約束してきた。ところがここ20年は昇給もなく、非正規は増加し、今では終身雇用も崩れかかっている。
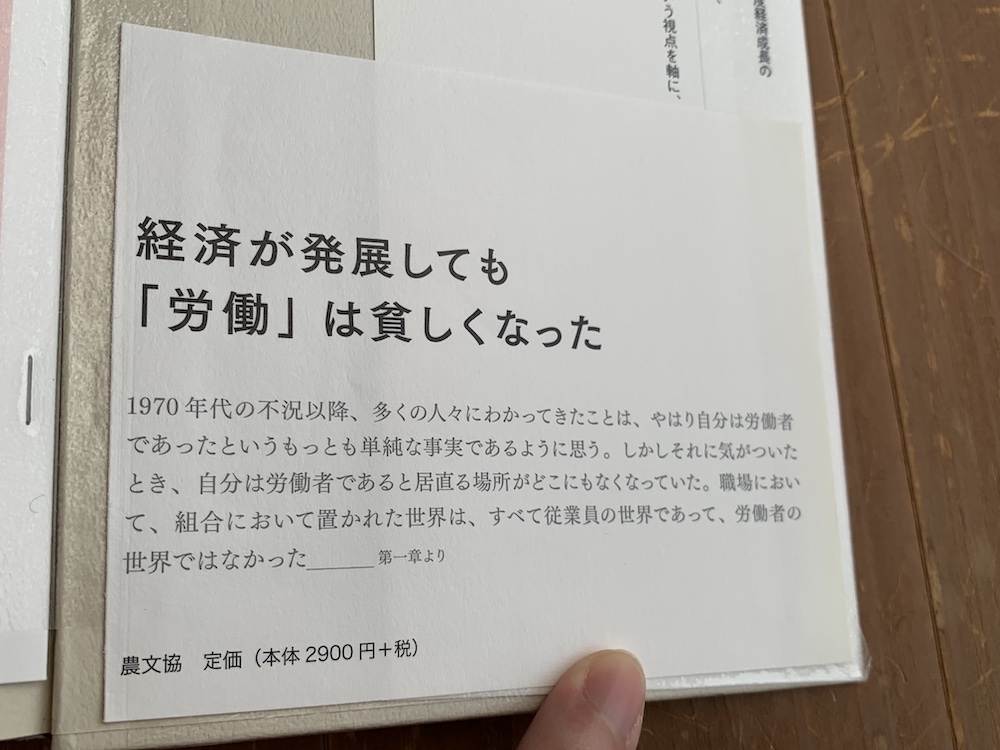
さて、他にも今回読んだ著作集3には印象的な箇所が多いので、あとはそこからいくつか備忘録的に抜書きしておこう。以下、マーカーでの強調は清水による。
本来なら労働者は、まず労働の場面で個人の労働権をもっていなければならない。そして次にお互いの労働権を認めあいながら、協同の仲間を発見していかなければならないのである。
p.66
日本の労働者の悲劇は、この基本が崩れてしまっているところにある。出発点の労働の場で彼らは従業員でしかない。企業という共同性のなかに身を置くことが日本の労働者の労働意識のはじまりである。そして労働権とお互いの労働の尊重がないところでは、労働者の連帯もまた確立しうるはずがないのである。
現在の日本の労働者は従業員でしかないという。考えてみると一時期叫ばれていた「働き方改革」というものも、その内実は「雇われ方改革」だったように思う。「労働する」ということは「従業する」とほぼ同義になってしまったのだ。
一見すると製鉄所などに導入された連続自動工程と労働集約型のライン生産方式は、全く正反対の生産形態であるようにみえる。だがそのどちらもが、人間がそれまでおこなってきた労働を科学的・客観的に計測することを出発点にしている。かつて労働過程は、労働者自身がもっている労働能力に全面的に依拠することなしには成立することはなかった。その労働能力はそれまでの労働によって培われた。いわば労働現場は労働者にまかせることによって労働過程を成立させるのである。
p.76
現代資本主義はこのような労働過程のあり方に対して挑戦してきた。二十世紀に入ってアメリカで成立するフォード、テーラー・システムなどは、生産過程を労働者にまかすのではなく、はじめに商品の生産過程を創造しその生産過程に労働者を配置する、さらに労働内容をも生産過程があらかじめつくりだしておく体制への転換の試みであった。いわば労働能力に依拠して生産が実現する体制から、生産過程の論理に従って労働をする体制への転換である、それを私は生産過程が労働過程からの自立性を確立していく過程ととらえている。
労働者がそのあり方を崩されていったその主犯はアメリカのフォード、テーラー・システムであると指摘される。アメリカではその生産方式は戦争よりずっと前に成立したが、日本で本格的に導入されたのは1950年代後半であるという。これが高度成長を呼び込んだ。と同時に、古い労働者の世界を解体してしまった。
資本のもとでの賃労働の平準化、賃金労働者の平等化の進行は市民社会そのものを起伏のない社会としてつくりだした。たとえば現在のようにすべての人間が「中流意識」をもつというようなことは、この資本のもとでの平等という構造的変化をみずにはその意味するものは理解できないように思われる。日本では戦後技術革新がテーラーのめざしたものを、決定的に確立していったとき、いわゆる大衆社会状況がつくられてきたのであった。現代市民社会の論理がそこにみえてくる。労働の質と量が「科学的」に管理されるようになった結果生みだされたものは、労働の疎外の進行、労働がつまらなくなった、ということには終わらなかった。賃労働、あるいは労働力商品の質を変えたばかりでなく、労資関係を変革し、資本制社会総体をも変えていった。
p.192-193
この著作は「一億総中流」という言葉がまだ現役だった頃のものだ。しかし、内山氏はその渦中においてすでにその問題点を指摘している。
労働意識、それははじめにのべたように、労働者が自分の労働の世界を築くという目的意識性を所有したときはじめて成立するものである。それは労働をとおして仲間や社会を発見していく、そのような労働者にしかわからない労働者の意識である。
p.292-293
しかし、これまでの検討で明らかにしてきたように、戦後の日本では例外的にしか労働意識は成立してこなかった。それゆえに労働者の労働観は、技術革新と高度成長期の展開のなかでしだいに市民的価値観とかさなりあいながら企業内従業員の意識へと変貌していったのである。労働にたいする肉体的・感覚的な不満は、ひとつの必要悪とみなされることによって解消されていった。
この状態が維持されるかぎり、これからの日本の労働者はいっそう無力な存在になっていくだろう。高度成長期の終息以降の社会で、自分だけの「高度成長期」を個人個人がおいもとめるしかないからである。
「自分の労働の世界」という言葉が重たい。今日ではそんなものは夢想すらできなくなっている。
しかし、インターネットの出現によって労働は企業から解放されつつある。個人個人が労働を創っていける状況になった。長い平成の停滞を抜けて、今やようやく「自分の労働の世界」への可能性が拓けたのではないだろうか。私はそんな希望を持っている。
